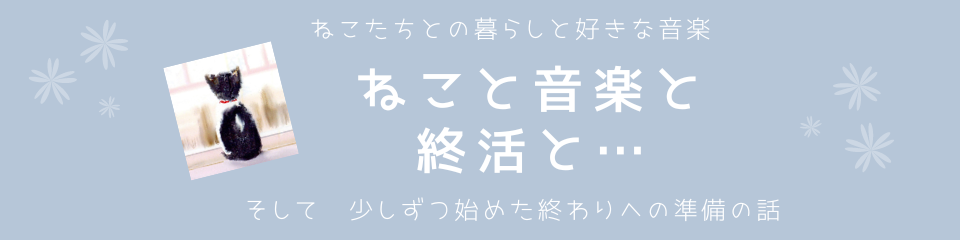私には入る予定のお墓がありません。
2016年に旅立った夫は献体をして、大学の合同墓地に眠っています。
(我が家のお墓事情については「【終活】60代おひとりさま、0から始めるお墓の話」をご覧ください)
終活の一環として、自分の埋葬方法について改めて向き合ってみたところ、いくつかの選択肢が浮かびました。
その中のひとつが「樹木葬」です。
ここでは、「樹木葬」の定義や特徴、種類と費用、メリットデメリットなどの基本情報を整理してみようと思います(時々、率直な感想も入っています)。
そのあと、私はどうするのか、どう選ぶのかを考えていきます。
樹木葬とは?定義と特徴
ここ数年、よく耳にするようになった「樹木葬」というワード。
最初に「樹木葬」の定義と特徴についてまとめます。
樹木葬に定義はない!?
一般的に「樹木葬」とは墓石の代わりに樹木や草花を墓標とする埋葬方法(ここですでに「え?草花?」と思っている…)で、実は明確な定義はないそうです。
私は「樹木葬=木の根元に埋葬若しくは散骨される」と思っていたので、これはなかなかの衝撃…。
つまり「樹木葬」とは…
で、さまざまな形が広く「樹木葬」と呼ばれているのです。
樹木葬の特徴
「樹木葬」は以下の特徴があります。
- 継承を前提としない(基本的に永代供養)
- 墓石不要のため初期費用が安い
- 環境への負担が少ない
- 宗教色が薄く誰でも利用しやすい
自分の代で終われるということが今までのお墓の概念と違うところだと思います。
場所によって規定に違いはあれど、基本的に永代供養なので安心です。
宗教に縛られない(ことが多い)というのも、父の時に苦い経験があるので助かります。
今の私にはどの特徴もかなり魅力的。
次に「樹木葬」の種類について調べます。
樹木葬の種類
「樹木葬」には定義がないため様々な種類がありますが、
- 環境による分け方
- 埋葬方法による分け方
の2つに分類されます。
環境による分け方
樹木葬を環境で分けると以下の2つになります。
里山の自然を活かした広い土地にシンボルツリーがあり、その下に埋葬するスタイル。
広い1区画に1本の木を植えるパターンが多く、地方や郊外に多くみられます。
霊園などに人工的に樹木や草花を植えて整備された緑地に埋葬するスタイル。
里山型に比べて1区画は小さくなります。
都市近郊に多く見られ、アクセスの良さも魅力のひとつです。
埋葬方法による分け方
樹木葬を埋葬方法で分けると以下の3つになります。
ひとつの大きな区画に複数の遺骨をまとめて埋葬する方法
遺骨は粉骨し土に還る素材の袋に入れてシンボルツリーの下に埋葬する(周辺に撒く方法もある)
シンボルツリーの下にあるカロートにそれぞれの骨壺に入れた複数の遺骨を埋葬する方法
※カロート:お墓の中で遺骨を納める場所(納骨室とも呼ばれる)
1区画にひとり分の遺骨を埋葬する方法
家族で1区画を使用するタイプやペットと一緒に入れるタイプもある
どちらの分け方から探すことも可能ですが、どちらかというと環境(場所)から探すことが多いのではないかと思います。
次に実際の費用についてです。
樹木葬の費用
樹木葬は墓石(約120~170万円)が不要なため、従来のお墓よりは安くなります。
以下は埋葬方法別費用の相場です。
| 合祀タイプ | 5~20万円 |
| 集合タイプ | 20~60万円 |
| 個別タイプ | 50~150万円 |
個別タイプの金額に幅があるのは、家族での使用やペットも入る場合があるためです。
基本的な費用の内訳は以下の通りです。
- 使用料:霊園や土地を使用するための費用
- 埋葬料:遺骨を埋葬するための費用
- 彫刻料:墓標となるプレートの設置や彫刻にかかる費用
- 管理料:霊園の維持管理にかかる費用(発生しない場合もある)
これらそれぞれの費用が埋葬方法によって変わってきます。
樹木葬の手続きの流れ
樹木葬に興味を持っても、「実際にはどう進めるのだろう?」と思いますよね。
私自身が調べた範囲で、契約前の準備から納骨までの流れを整理してみました。
(※施設によって多少の違いはあります)
生前の準備
①場所を決める
希望する地域や霊園・寺院で樹木葬を扱っているか調べる。
種類(個別型・共同型・合祀型)や費用、アクセスなどを比較して決定。
②現地を見学する。
いくつかの候補に実際見学に行く。
雰囲気や管理体制、職員の対応などを確認する。
③契約・入金
説明に納得できたら契約書に署名し、永代使用料などを支払う。
契約後に「墓地使用許可証」が発行され、正式に区画が確保される。
亡くなった後から納骨まで
①死亡届の提出
医師の死亡診断書をもとに、市区町村へ死亡届を提出すると火葬許可証が発行される。
(葬儀屋が代行してくれる場合もある)
②火葬
火葬場で火葬を行うと、火葬後に「埋葬許可証」が交付される(火葬許可証と一体化している場合もある)。
③納骨する日を決める
霊園や寺院と納骨の日程を相談する。
④納骨式
埋葬許可証を持参し、指定された区画に遺骨を納める(住職による読経などを行う場合もあるが、無宗教での納骨も可能な施設もある)。
大体このような流れです。
(亡くなった後の手続きを任せる人がいない場合については後日まとめます)
樹木葬のメリットデメリット
次に、私が感じた樹木葬のメリットデメリットをまとめました。
樹木葬のメリット
☆費用が安い
☆継承不要(永代供養)
☆宗教に縛られない自由さ
☆都市近郊でも選べる
☆自然に還れる
樹木葬のデメリット
★墓標がわかりにくい場合がある
★合祀タイプは遺骨を取りだせない(再埋葬不可)
★新しい形式のため違和感を感じる人もいる
★里山型は交通の便がよくない場所もある
樹木葬の選び方のヒント
ここまで樹木葬の基本情報をまとめてきました。
私の現時点での状況を鑑みると樹木葬という選択はかなり魅力的です。
もし私が樹木葬にするならどのように選ぶのだろう…と考えてみました。
場所から探す
私の場合は場所から探すことになると思いました。
自分がそこにお参りに行くわけではありませんが、なじみのある土地や雰囲気が自分好みの霊園などが選ぶ基準のひとつになります。
地元や今住んでいる地域などから探し始めて範囲を広げていく感じかなぁと思います。
埋葬方法から探す
場所にこだわりがなければ埋葬方法から探すというのもアリだと思います。
たとえば里山型樹木葬の合祀タイプから探す…とか、都市型樹木葬の家族も入れる個別タイプから探す…といった感じです。
今の時代はネットで全国から探すことも可能ですから。
おわりに
以上、「樹木葬」について調べたことをまとめてみました。
私自身が樹木葬にするかどうかはまだ未定ですが、なかなか魅力的だと感じています。
他の方法(海洋散骨や献体など)についても調べてまとめますので、また覗きにきていただければと思います。
自分の納得いく方法を見つけられますように。
私は静かに地球の一部として還っていきたいのです。
土になり、風となり、そして新しい命のはじまりにそっと関われたら…そんなことを考えています。