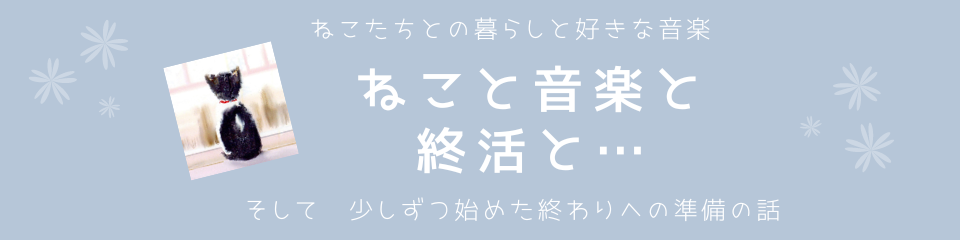私には入る予定のお墓がありません。
(我が家のお墓事情については「【終活】60代おひとりさま、0から始めるお墓の話」をご覧ください)
現在、60代おひとりさまとして静かに終活を進めています。
これまでに「樹木葬」や「海洋散骨」など、自然に還るかたちの供養について調べてきましたが、今回は「献体」という選択に向き合ってみようと思います。
実は私の家族には、献体を選んだ人が4人います。
古い順に、父、義母、夫、そして今年始めに旅立った母です。
父、義母、夫は同じ大学に献体していますが、母だけは手続きが間に合わず、その願いは叶いませんでした。
この経験を通して、献体の登録方法や注意点、事前に確認すべきことなどが見えてきました。
ここでは、家族の体験をもとに、献体の流れと実際に起こり得る課題について、わかりやすくまとめていきます。
はじめに:献体とは?
献体とは
家族の献体体験
ここで家族が献体した時のことを少し書いてみようと思います。
父(1987年)
享年53歳。
もう40年近く前になります。なので、記憶もかなりあいまい。
義母(2013年)
享年92歳。
義母は半年の入院の後この世を去りました。
自宅で倒れて救急搬送されるまで、何一つ病気をしたこともなく、自分の身の回りのことは全て自分でやっていました。
亡くなったのは夜、翌日献体する大学の職員が2名病院に迎えに来ました。
私と夫と娘も病院へ。
そこで夫は何枚かの書類に記入をしました。
そしてそのまま大学へ搬送されるところを見送りました。
義母が高齢で直接の知り合いはもういなかったことから、葬儀はしていません。
夫(2016年)
享年55歳。
夫は自分の身体の不調をネットで調べ、勝手にとある病名にたどり着きました。
独立している子どもたちを呼び、自分はもう長くないと思うと話しはじめ
「今家にいる猫たちを手放さないでほしい」
「献体をしたい」
母(2025年)
享年88歳。
母も生前「献体しようと思っている」と話してはいたもののまだ手続きはしていませんでした。
2024年12月26日インフルエンザで入院。
何度かの危篤を経た年明けにようやく献体の手続きに入りました。
そう、年末年始を挟みいろいろスムーズにはいかなかったのです。
大学との電話でのやり取りの中で「本人が名前を書くことは難しいか」と聞かれ危篤であることを伝え「無理です」と答えました。
生前の本人の意思が確認できているなら代筆もやむを得ないとのことで、書類の調達となり、郵送ももどかしいので直接取りに行きました。
4人の同意が必要だったので、母にとっての子供3名と孫1名で署名しました。
その翌朝未明に母は旅立ちました。
この時点でまだ書類は大学側に届いていません。
前日書き終わった時点で、郵送するより翌日持参した方が早いと考えていました。
そして母が亡くなった日の朝、家族が書類をもって大学へ向かう中、私が大学へ現状を伝える電話を入れました。
たくさんのお悔やみの言葉と共に遠慮がちに申し訳なさそうに
「亡くなってからの受付はできない」
という趣旨のことが伝えられました。
生前に書類の受付を終えていることが献体の必須条件だそうです。
言われてみれば、過去の経験からもわかっていたはずのことでした。
でも、当時の私はあまりにも急にいろいろなことが起こりすぎて、そこに考えが至りませんでした。
さらに、大学側との数回の電話のやり取りの中で、一度も「生きているうちに受付できなければ献体できない」とは言われませんでした。
その点については念のため確認。
電話対応してくださった職員の方からは「前回のお電話の最後に『どうぞご存命であられますように』と申し上げましたのでご理解いただけたかと…言葉が足りずに申し訳ありませんでした。」という回答でした。
思うことはいろいろありましたが、献体をできないことは確定なので、大学に向かっている家族を止めるべく電話を切りました。
この年末年始のあらゆる出来事(ほかにも騒動は多々あった)は一生忘れないと思います。
この出来事をきっかけに、家族の中には「自分も献体をするつもり。今から書類をそろえておくので署名してね」と言う者もいました。
献体の登録の流れと注意点
ここまでの経験を踏まえて、改めて献体の登録の流れをまとめたいと思います。
簡単な登録の流れは以下の通りです。
- 申込書の請求
- 申込書の記入と返送
- 会員証の受け取り
最大の注意点は以下の2点です。
- 生前に登録完了すること
- 本人の希望であること
流れを順番に説明しますね。
申込書の請求
基本的には献体できるのは献体希望者が住んでいる都道府県にある医科(歯科)大学もしくは大学医学部(歯学部)です。
大学によっては近隣の市区町村も受付可能としているところもあるので確認してください。
さらに申し込み条件(居住地・年齢・同意親族の人数など)を満たしているかの確認も必要です。
申込書は大学または献体篤志家団体(献体の会)に請求します。
「献体」を志す人々が集まり、大学と協力して献体運動を推進する団体のこと
医科(歯科)大学もしくは大学医学部(歯学部)や地域ごとに設立されている
代表的な団体:白菊会、日本篤志献体協会など
申込書の記入と返送
申込書が届いたら書式通りに記入します。
ここで一番重要なのは「家族(親族)の同意」を得て署名をしてもらうことです。
署名が必要な人数は大学によって違いますが、署名してもらう人以外にも説明しておいた方がいいと思います。
生前に本人が献体を希望していても、死後に献体を実行するのは遺族です。
きちんと説明して理解してもらわないと、亡くなった後に献体が実行されないこともあり得るのです。
署名できる肉親の範囲は大学によって違うので確認が必要です。
記入が終わったら大学へ返送します。
会員証の受け取り
申込書を提出して受理されると、会員証(献体登録証)が送られてきます。
常に携帯しておく方がよいと思います。
会員証には献体先の大学名・死亡時の連絡方法などが記載されています。
これらは家族にも知らせておきましょう。
献体登録時の注意点
注意点は以下の通りです。
- 生前に登録完了していること
- 本人の意思であること(代筆は原則不可)
- 家族の同意が必要(署名人数は大学によって異なる)
- 登録大学の地域に居住していること(転居した場合は再登録が必要なこともある)
- 会員証は常に携帯し、家族にも情報共有しておく
特に、生前に登録完了していることと家族(親族)の同意を得ることは重要だと思います。
家族(親族)へは自分の意志がきちんと実行されるように必ず同意を得ておきましょう。
登録後もできるだけ多くの身近な人に理解してもらえるように、自分の意志を伝えておくことが大切だと思います。
また、運搬費用・火葬費用は大学側の負担となりますが、葬儀費用は遺族の負担となります。
献体できないケース
ここでは献体できない場合について説明します。
いくら本人が希望しても献体には適さないこともあります。
- 感染症がある場合(HIV・肝炎・結核など):医学生や職員への感染リスクがあるため
- 事故死や遺体損傷が激しい場合(轢死・溺死・焼死など):腐敗防止処置ができないため
- 死後の発見が遅れた場合:死後数日以上経過していると適切な処置ができないため
- 病理解剖・司法解剖を受けた場合:遺体の状態が変化することによって全身の解剖が困難になるため
- 臓器提供を行った場合(※献眼は可能な場合あり):臓器が提供されると解剖実習には適さないため
- 遠隔地で亡くなった場合(搬送が困難):近隣の大学に献体できる場合もあり
おわりに:私が今思うこと
「樹木葬」「海洋散骨」に続いて「献体」についてまとめてみました。
「献体」は家族が選んだこともあって、私にとっては身近なものです。
最後の社会貢献という意義も大きいと思います。
ただ、私は臓器提供も考えているので、それによっては献体は叶わないかもしれません。
まだ自分の中でどうしたいか決め切れていないので、これからいろいろ考えたいと思っています。
「献体」をすすめているわけではなく、こういう選択肢もあるということは知っていてもいいのではないかと思い書きました。
私自身も考えていきたいと思います。