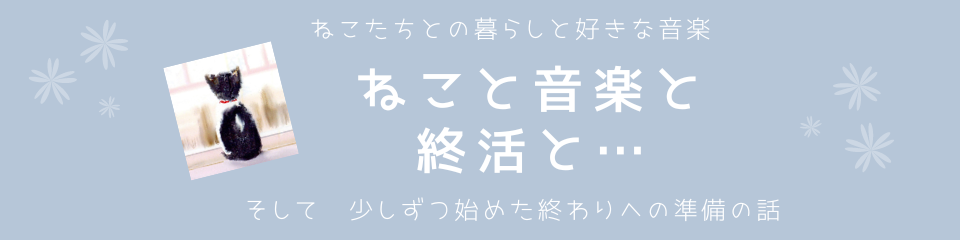はじめに
今の私には入る予定のお墓がない。
私の終活において最大の難関ともいえるお墓問題。
何も準備をせず、もしものことがあったとしたら…
子どもたちがどうにかするしかないし、それについてどうこう言えるわけもないけれど、
それはちょっと酷だよね。
理想は「こうしてほしい」という明確な段取りの提示。
それが間に合わなかったとしても「せめてもの指針」を残すべく、自分の行き先を考えなくては。
ここでまず思い出すのが夫の実家のお墓のこと…
夫の実家のお墓
夫の実家のお墓は(ここから200kmくらい離れた)他県の市営霊園。
そこに夫の父が眠っている。が、夫の母は生前そこに入りたくないと言っていた。
「今さら一緒になったってしょうがないじゃない。あたしは嫌なのよ。」
夫の父は若干?破天荒だったようで、夫の母はいろいろ大変だったそう。
そんな話も聞いていたので、まぁまぁまぁ…笑
夫も「誰がそのお墓に入っているのかよくわからない…なんか遠い親戚のところに入れてもらったような…」
いや、その記憶はどうなん???確認しようとは思わなかったん???笑
と心の中で突っ込まないわけでもなかったが、これ以上聞いたところで正解は出てこない。
「またか」と思うエピソードがひとつ増えたに過ぎなかった。
そう、ちょっと夫の家族は変わっている。
結婚した時にまだ二十歳だった私。
すでに亡くなっていた夫の父のお墓参りに行かなくていいのか尋ねた。
「え?いいよ、遠いし。俺も行ってないし。」
えーーーーー!!!さすがの私もそれはどうかと思ったので夫の母にも同じことを尋ねた。
「あら、行きたいの?遠くて大変だからいいわよ。」
お、おう…なんかもうただただびっくり。
でも、二十歳の小娘は「だったらいいか!」とそれっきり。
びっくり&それっきり(笑)
その後に結婚した夫の姉はちゃんとお相手とお墓参りに行っていたという…
なんだよ~もう。
最終的に、夫の母も夫もそのお墓に入ることはなかった。
そして私の実家についてもまたちょっと特殊で…
私の実家のお墓
私の実家もお墓はない。
父が亡くなってもう40年近く経つ。
享年52歳。
そのころの私はお墓について何も知らず、父の実家のお墓に入れてもらえばいいと思っていた。
が、宗教上の理由でそれは叶わなかった。
さぁ大変!笑
結局、母が通っていた教会のお墓で眠っている(多分、相当片身狭い笑)。
そして今年の初めに母も亡くなった。
秋にその教会のお墓に入れてもらう予定。
親の代はそれぞれの事情があったため私たちも考えなくてはならなくなった。
では、夫はどういう旅立ちを選んだのかというと…
夫の選択:献体
夫は体調不良で自らもう長くないと悟った時に私と子どもたちにこう言った。
「献体をしたいからこの書類にサインしてほしい。」
その翌日、地元の病院を受診した際、その場で担当医が大学病院に予約を入れた。
そして大学病院へ向かう途中で献体の書類をポストに投函。
そこから3週間の入院を経て帰宅、通院しながらの在宅療養となった。
退院から10か月、最初に受診した病院の緩和ケアを勧められ、そこから1ヶ月半後に他界した。
夫は今、献体した大学の合同墓地に眠っている。
夫が亡くなる3年前に夫の母が選択した場所でもある。
献体したからといって必ずそこに入らなくてはいけないわけではない。
遺骨を受け取り自分たちの用意したお墓に入れる方々もいる。
我が家の場合、夫が亡くなった時にお墓を建てるという選択肢はなかった。
経済的に難しかったことは夫自身も百も承知だったと思う。
それゆえの選択だったのかもしれないとも思っている。
そしていよいよ私自身の選択を考える時がきた…
私の選択:検討開始
というわけで私のお墓について考えてみようと思う。
ここは人それぞれの考え方があると思うので、あくまで「私の場合」。
子どもたちへの負担が少なく、私らしい方法はなんだろう。
パッと思いついて調べてみようと思ったのは以下の4つ。
- 樹木葬:自然に還る①(形態もいろいろあるらしい)
- 海洋散骨:自然に還る②(海も意外といいかも)
- 永代供養:管理不要で子どもたちの負担は少ない
- 献体:最後の社会貢献
これらについて、ひとつひとつ調べながら私の最適解を見つけていきたい。
おわりに
正解があるわけではないと思う。
だからこそ私の好きな方法で人生を締めくくりたい。
今、考える力があるうちに…選ぶ能力があるうちに…
静かに、私らしい選択を見つけてみようと思う。